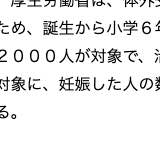朝日新聞によると
世界で大流行した「スペイン風邪」と呼ばれるインフルエンザのウイルスが、ウイルスに対抗する免疫機能の異常を引き起こす強い病原性によってサルを死なせてしまうことを、河岡義裕・東京大医科学研究所教授を中心とする日米カナダの研究グループが実験で示した。18日付の英科学誌ネイチャーで発表する。
1918年から数年間猛威をふるったスペイン風邪は、全世界で4000万人の死者を出したとも言われている。その後、残されていた当時の標本などからウイルスの遺伝子配列がわかり、同じウイルスを人工的に作り出せるようになった。グループは、人工ウイルスを生物学的にヒトに近いカニクイザルに感染させ、症状を調べた。
ヒトやサルはウイルスに感染すると、その活動を阻止しようとする免疫機能が体内で働く。ウイルスの増殖を阻止するため、インターフェロンというたんぱく質を分泌することなどが知られる。
ところが、この人工ウイルスに感染させたサルの場合、インターフェロンの分泌が抑えられるなどの異常が現れた。その結果、体内でウイルスが増え続けて肺炎や肺水腫を起こし、死に至ることがわかった。インフルエンザウイルスが、マウスなどに重い症状を起こすことは実験で確かめられていたが、サルの仲間で重症化の仕組みが確認できたのは初めてだ。
現在、アジアを中心に問題となっている鳥インフルエンザウイルスがヒトに重い症状を起こすのも、同様の仕組みで説明できる可能性がある。河岡教授は「さらに研究を進めることで、鳥インフルエンザや新型インフルエンザの治療に役立てたい」と話している。
(Visited 2 times, 1 visits today)